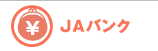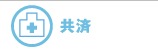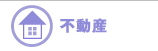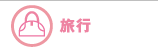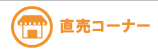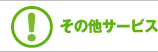あぐりキッズスクール
JA熊本市は、子どもたちに体験を通して農業や食の大切さを学んでもらおうと「あぐりキッズスクール」
を開校しました。今年も女性部、青壮年部と協力しながら、田植えや稲刈り、野菜や果物の収穫体験などの
開催を予定しています。
|
|
副知事に「エースピーマン」贈呈 現場からの声を届ける JA熊本市東部ピーマン部会
|
||||
市場担当者と連携 販売力強化目指す JA熊本市春夏瓜類、春野菜生産圃場視察会
|
カラー出荷最盛期 JA熊本市御幸カラー部会
|
地元の高校生受け入れ JAを学ぶ
|
||||
タケノコ出荷開始 旬をお届け JA熊本市芳野筍部会
|