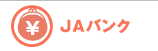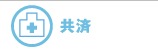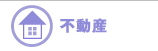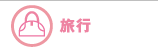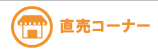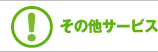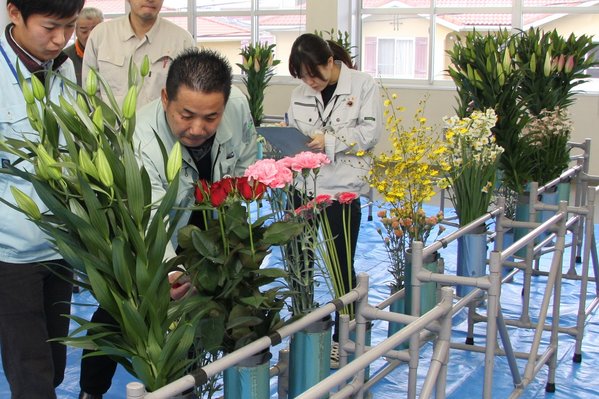- �g�b�v�y�[�W
- JA�̃T�[�r�X
- �e��T�[�r�X����̂��m�点
- �g�s�b�N�X
- �g�b�v�y�[�W
- �̌��I�H�Â���
- �g�s�b�N�X
- �g�b�v�y�[�W
- �g�s�b�N�X
- �g�s�b�N�X
������L�b�Y�X�N�[��
�i�`�F�{�s�́A�q�ǂ������ɑ̌���ʂ��Ĕ_�Ƃ�H�̑�����w��ł��炨���Ɓu������L�b�Y�X�N�[���v
���J�Z���܂����B���N���������A�s�N���Ƌ��͂��Ȃ���A�c�A������A���ʕ��̎��n�̌��Ȃǂ�
�J�Â�\�肵�Ă��܂��B
|
|
�C�`�S�@�N���X�}�X�Ɍ����ďo�׃s�[�N
|
||||||
��ĂĐH�ׂāu�Ђ���v�ɐe����
|
�암�x�X��ԕi�]��
|
�i�`�F�{�s��R�x�X�_�Y���i�]��
|
�̂̔_����g���đ哤�̒E���̌�
|
|||||||||