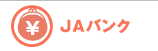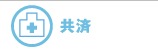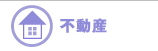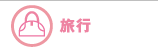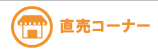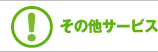あぐりキッズスクール
JA熊本市は、子どもたちに体験を通して農業や食の大切さを学んでもらおうと「あぐりキッズスクール」
を開校しました。今年も女性部、青壮年部と協力しながら、田植えや稲刈り、野菜や果物の収穫体験などの
開催を予定しています。
|
熊本市西区河内町のJA熊本市夢未来柑橘選果場で、ハウスみかんの出荷が始まりました。30日は、主に地元百貨店向けに1.5トン出荷。翌週からは出荷量も増え、日量2〜3トンを見込みます。
29年産は、梅雨入り後の雨が少なく、天候に恵まれたため、食味・外観ともに良好な仕上がりとなっています。総出荷量は例年並みの115トンを予定。出荷は7月から8月中旬まで全国各地、また地元の市場や百貨店に向けて出荷します。
ハウスみかんは、濃厚な甘みで、果肉が柔らかく、口に入れた瞬間のとろけるような食感が特徴。ビタミンCが豊富で、夏風邪予防に効果的と言われます。また、夏のお中元として、贈答用としての需要が高まっています。
JA管内では、JA柑橘部会ハウスみかん部の生産者5人が、2ヘクタールで生産しており、徹底したハウス管理で高品質なハウスみかん栽培に努めています。担当職員は「お盆前には全国各地からお買い求めのあるハウスみかん。今年も多くの消費者の方に高品質なものを味わってもらいたい」と話します。
|
 順調にスタートしたハウスみかん出荷 |
 高品質に仕上がっています |
|
|
JA熊本市は6月27日、第26回通常総代会を熊本県立劇場コンサートホールで開きました。出席総代343人が、2016年度活動報告、2017年度事業計画、JA熊本市の自己改革実践に関する特別決議、「平成28年熊本地震」から復旧・復興に関する特別決議など5議案を可決・承認しました。
16年度決算概要は、事業総利益39億308万円(計画対比5・4%増)、経常利益5億4,024万円(同163・0%増)。当期剰余金は2億7,278万円となりました。JAの宮本隆幸組合長は「トランプ新米大統領の誕生によるTPP協定発効の状況変化や新農協法・政省令・監督指針の施行など、JAをとりまく環境が大きく変わっている中で、組合員の皆様にはご理解いただき評価していただくことが何よりも大切です。」とあいさつしました。
17年度は、重点取り組み事項として、(1)熊本地震復旧・復興、(2)農業者の所得増大と地域の活性化、(3)農業・農協のアピール力強化、(4)職員の専門的知識の向上の4点を目標に掲げ、組合員・組織の負託に応え、組合員の生活向上・組織の発展を目指し、事業に取り組んでいきます。 |
 県立劇場コンサートホールで開催しました |
 議案を審議する総代 |
 あいさつする宮本隆幸組合長 |
|
 地鎮の儀で鍬入れする宮本組合長 |
JA熊本市は22日、熊本市東区健軍地区の建設予定地でJA熊本市健軍支店新築工事の起工式を行いました。式にはJA役員や同支店管内の組合員、工事関係者など約60人が出席。参加者等は工事の安全と無事完成を祈願しました。
熊本地震で被災し甚大な被害を受けた健軍支店は、現在、湖東支店内に仮事務所を設け営業しています。宮本隆幸組合長が「これまで以上に組合員・地域住民から親しまれる事務所になるように。なお一層の農協事業の発展にご尽力を。」と、上田徳行担当理事が「組合員の皆様の協力のもと、安心して利用できる施設が完成することを期待したい」とあいさつし、健軍支店の新築を祈念しました。
施設は鉄骨造平屋建ての延面積は387.08平方メートル(約117坪)。平成29年10月下旬に竣工予定です。
|
|
|
JA熊本市青壮年部竜田支部は21日、小学生に田植え指導を行いました。熊本市立龍田小学校の5年生121人と龍田西小学校の5年生91人が、青壮年部員の指導のもと、種から育てた「くまさんの力」約8アールを手植え。青壮年部が毎年、食農教育の一環として行っています。後藤新介部長をはじめとする部員8人は、丁寧に田植えの仕方を説明し、児童らと一緒に作業を行いました。
圃場を管理する松岡公子さん(63)は「米づくりを体験することで、普段食べているお米や食べ物がいかに尊いものなのかを理解してほしい」と話し、子ども達の農業への理解促進に期待を寄せました。
児童らは、水田のぬかるみに戸惑いながらも、青年部員に指導を仰ぎながら積極的に手植えに取り組みました。作業後には、「最初は難しかったけど、自分の手で田植えできてうれしい。」と感想を話しました。田植えした米の収穫は10月中旬に予定しており、児童たちは収穫作業を行う計画です。 |
 苗の植え方を説明 |
 生産者と児童が一緒に田植えしました |
|
|
熊本市西区河内町の白浜水田保全組合は19日、河内小学校の児童と田植えを行いました。米づくりを知り、農業の大切さを学んでもらおうと毎年行っており、今年で11回目。坂本信一組合長は「子どもたちに、机の上ではなく、実体験として農業を学んでもらうことに意味がある。」と話します。
5年生の児童23人は、生産者に手植えの仕方を教わりながら「くまさんの力」を約1アール植え付けました。児童たちは、水田のぬかるみに歓声を上げながら田んぼに入り、熱心に手植えに取り組みました。担任教諭の長尾妃月さん(23)は「授業の一環でバケツ稲を育てて稲の育て方や成長を観察し、米づくりを学んでいる。実際の田植え体験は、児童たちにとって農業への理解を深める良い機会になった。」と感想を話しました。
田植え作業後には、生産者への質疑応答が行われ、児童たちからは「稲の宿敵は何ですか」など、米づくりに関する様々な質問が投げかけられました。児童たちは10月には稲刈り体験を行い、収穫した米を食べる計画です。 |
 泥だらけになりました |
 1列に並んで田植え体験 |
|